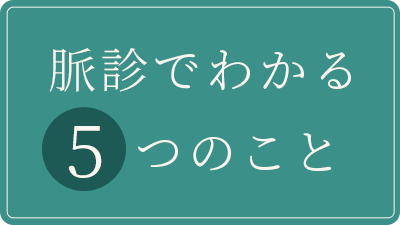カリキュラム
当会は脈診と経絡治療をマスターするための実践的なカリキュラムがあります。
先ず「入門基礎講座」から脈診と経絡治療の学習はスタートします。
次に臨床で抜群の効果を発揮する単元・コンテンツが詰まっている臨床コースと呼んでいる「初級コース」と「中級コース」があります。
更に脈診と経絡治療を深く探究・トレーニングしていく「上級コース」があります。
もっと脈診と経絡治療を更に深く探究していく「S級コース」を2024年度から開設しました(ホームページは現在建設中)。
初級コースと中級コースそして上級コース、S級コースは年間を通して受講するスタイルです。
これらの年間カリキュラムのコースに加わらない「特別講義」があります。
2024年度カリキュラム 年間スケジュールと受講料
入門基礎講座 一般受講料66,000円 早割受講料55,000円
第1回
オンライン形式:2024年9月22日(日)9時~12時
オフライン形式:2024年10月6日(日)10時~17時
第2回
オンライン形式:2025年3月30日(日)9時~12時
オフライン形式:2025年4月6日(日)10時~17時
各回の講義内容・実技内容の詳細については後述
初級コース 継続受講料121,000円 一般受講料133,100円
2024年
9月29日 急性頚部痛・急性腰背部痛の鍼灸治療
10月14日 末梢神経障害の鍼灸治療
11月24日 膝関節痛の鍼灸治療
12月15日 肩関節痛の鍼灸治療
2025年
1月26日 急性外傷の鍼灸治療
2月23日 感冒・アレルギー性鼻炎の鍼灸治療
3月23日 頭痛の鍼灸治療
4月20日 高血圧症の鍼灸治療
5月25日 便秘症の鍼灸治療
6月22日 下痢症の鍼灸治療
7月20日 逆流性食道炎の鍼灸治療
中級コース 継続受講料145,200円 一般受講料157,300円
2024年
9月29日 月経痛の鍼灸治療
10月14日 不妊症の鍼灸治療
11月24日 妊婦さんへの鍼灸治療
12月15日 更年期障害の鍼灸治療
2025年
1月26日 皮膚疾患(アトピー性皮膚炎・蕁麻疹)の鍼灸治療
2月23日 起立性調整障害の鍼灸治療
3月23日 動悸・不整脈の鍼灸治療
4月20日 うつ病の鍼灸治療
5月25日 眩暈・目眩・めまいの鍼灸治療
6月22日 甲状腺機能亢進症の鍼灸治療
7月20日 関節リウマチの鍼灸治療
上級コース 継続受講料154,000円 一般受講料165,000円
カリキュラム 講義内容と実技内容
入門基礎講座
脈診は六部定位脈診と脈状診の基本となる八祖脈を中心に学習していき、脈診に親しみ慣れていきながら経絡治療の基礎をしっかりと身に付けていきます。
先ず3~4時間ほどオンライン形式にて講義内容を受講し、脈診と経絡治療の概要と治療の流れまでしっかりと理解していきます。
次に6時間ほどオフライン形式にて講義内容を実践し、脈診と経絡治療を練習していきます。
- 一般的には三本の指で脈を診るのに、人差し指だけで脈を診る理由って?
- 六部に配当されている十二経脈と五(六)臓六腑は何故その位置に配当されたの?
- 脈って本当に上(浮)の部分と下(沈)の部分に分かれているの?
- 同じ位置で診ているのに浮の部と沈の部を感じることはできるの?
- 証を立てる効率的な方法って?
- 脈診から考える疾病(病気)になる本当の理由って?
- 診察、診断そして鍼灸治療するにあたって運用する陰陽五行って?
- 本治法で使用される経穴は何故その経穴を選択したの?
- 沢山ある鍼灸の手技の中、補法って?
- 陰経脈の深さとその深さが設定した理由、その覚え方はあるの?
- 難経六十九難の『虚すればその母を補い~』ってどういうこと?
- 本治法をする意義や目的とは?
- 腹部募穴を選択した理由は?
- 腹部募穴を補法する意義や目的とは?
- 主証と客証って?
- 難経六十九難の『実すればその子を瀉す』ってどういうこと?
- 標治法と局所治療は違うの?
- 陽経脈の深さって?
- 何故、標治法は瀉法するの?
- 局所治療と標治法は違うの?
- 何故、局所治療は補法なの?
全部で二十九脈あるとされる脈状。そのうち臨床で遭遇する機会の多い八祖脈を中心に脈の形状と臨床的意義を学習していきます。
- 七表・八裏・九道(動)の脈状の定義は?
- 虚脈、実脈、浮脈、沈脈、数脈、遅脈、滑脈、濇脈の形ってどんななの?
- 虚脈、実脈、浮脈、沈脈、数脈、遅脈、滑脈、濇脈のそれぞれどんな意味(臨床的意義)があるの?
- 虚脈が主証を決める際に重要視するのはなぜ?
- 沈脈が起きる状態って身体の中ではどのようなことが起こっているの?
- 浮脈が起きる状態って身体の中ではどのようなことが起こっているの?
- 実脈が起きる状態って身体の中ではどのようなことが起こっているの?
- 数脈が起きる状態って身体の中ではどのようなことが起こっているの?
- 遅脈が起きる状態って身体の中ではどのようなことが起こっているの?
- 滑脈が起きる状態って身体の中ではどのようなことが起こっているの?
- 濇脈が起きる状態って身体の中ではどのようなことが起こっているの?
臨床では症状の急性期と慢性期では施術を展開していく手順が異なります。
急性期では標治法から、慢性期では本治法からアプローチし始めます。
この施術を展開していく順序の原則を入門基礎講座で学び、その実践を初級コースで学ぶための重要な単元になります。
- 本治法と標治法の施術する順序は決まっているの?
- 局所治療や特効穴はどのタイミングで行うの?
- 背部兪穴や腹部募穴はどのタイミングで行うの?
- どんな場合の時に標治法からアプローチするの?
- 標治法からアプローチし始めてその後はどのように治療を終えるの?
- 何回か検脈(脈診)するタイミングで何を確認しているの?
- 学校教育で学習することは異なる背部兪穴の取穴方法は?
撓骨動脈に配当されている十二経脈、五(六)臓六腑の取り方と診る方法を自分自身と他の受講生で確認し合い、経絡治療の手順の中で最も重要な「証」を決定していきます。
脈診から得られた身体の虚実などの情報から経絡治療へとつなげていきます。
最初は経絡治療のデモンストレーションを観ながら脈が変化していく様子を時間しながら講義内容の理解を深めます。
病の根本を治す方法で使われる経穴の選ばれた理由と、本治法と腹部募穴に使用する「補法」の鍼の操作(手技)を練習します。
脈診から得られた脈証の正誤に加えて六陰経の流れている深さを確認できる瞬間です。
経絡治療の全行程と手順は本治法、標治法、局所治療に大別されますが、その理論は難経六十九難によって導き出されています。
脈診から導き出された経脈と臓や腑を整える方法の意義と目的について学習し、標治法に使用する経穴を中心に瀉法の手技を練習します。
背部兪穴は施術効果を持続させるうえで経絡治療には絶対に不可欠な施術手順です。
そのアプローチ方法に加えて背部兪穴を見付ける(取穴する)方法を共有します。
全部で二十九脈あるとされる脈状。そのうち臨床で遭遇する機会の多い八祖脈を受講生同士で脈を診合い、それぞれ該当する脈状を打っていることを検脈して把握できる大切な単元です。
これまで説明してきた通り、経絡治療家は脈証、つまり脈診で診断(証立て)して経絡治療を展開していきます。
臨床では同じ症状、例えば腰痛や生理痛などの症状に経絡病証と臓腑病証が存在するため、これらを判別する必要があります。この判別はより詳細な病態把握と経絡治療する際の刺鍼深度など刺激量を把握するからです。同じ腰痛でも経絡病証と臓腑病証とでは東洋医学的診断(証立て)の導き方や刺鍼深度などを含めた刺激量が全く異なります。
脈診の初歩で学習する六部定位脈診で得られた情報だけでは証を間違えてしまう、誤った診断(証立て)つまり「誤診」をしてしまいます。その結果のまま経絡治療を行うと「誤治」となり、患者様を治すどころか悪化させてしまうことに成り得ますから経絡治療の効果を発揮できないことを痛感することになるでしょう。
この問題は脈状診を含めた六部定位比較脈状診を行うことで解消できますので、その観点と臓腑病証に対するアプローチ方法を共有します。脈診と経絡治療を習得するための最も重要な単元の一つであって、極意ともいうべき観点を学んでいきます。経絡治療の習得を目指した多くの先輩達が挫折していった課題の一つを入門基礎講座の最後に学習します。
そして次のステップとなる臨床コース(初級コースと中級コース)で経絡病証と臓腑病証の実際と実践を経絡治療が著効する症状別・症例別について学習しながら習得していきます。
- 病脈は強く打っている。どうやって証を決めればいいの?
- 病脈って強く打っているのはどうしてなの?
- 五臓六腑の臓腑って全部で17あるけど、残りの臓腑は何?
- 経絡病証と臓腑病証はどのような脈の違いが出るの?
- 経絡病証と臓腑病証をどうして誤診(誤った証立て)をしてしまうの?
- 経絡病証と臓腑病証の刺鍼する深さが2倍ほど違うのはどうして?
- 同じ腰痛や生理痛でも経絡病証と臓腑病証ではどのようなメカニズム(病理と病態)で症状がでるの?
- 経絡病証は外邪が病因、臓腑病証は内因や不内外因が病因になるのはどうして?
初級コース
来院頻度の高い疾病や症状に対して、入門基礎講座で習得した経絡治療にプラスして当会独自の鍼灸治療法を学ぶコースです。経絡病証をメインに病理・病証を考え、脈状で説明していきます。
実技では習得した経絡治療の基本の治療の流れに、症状別に著効するアプローチ方法を加えることで飛躍的に治療実績を上げることが可能になります。その観点と極意を漏れなく共有していきます。
一生涯の内、寝違いやギックリ腰を経験しない人はそう多くはありません。文字通り「身体の要」の腰と「十二経脈すべてが流注している」首に発症する急激な痛みに対して、運動制限に対して上肢や下肢の遠隔部への鍼灸治療で改善する方法を共有します。これまでその局所にしか鍼灸をしてこなかったことがなぜ本治法だけでもその痛みを変化させることができ得るのか。経絡を介したアプローチ方法の素晴らしさを実感することでしょう。
- 東洋医学では急性に発症する頚部痛・腰背部痛をどのように考えるのか?
- 痛みが激しくて横になれない首の痛みへの対応方法は?
- 激しい腰の痛みで臥位になれない患者様への対応方法は?
- 痛みは無いけど首が動かせない場合の鍼灸治療は?
- どこに通院しても治らない腰痛の鍼灸治療は?
- 治療の際の注意点はどのようなものがあるのか?
- 患者様への適切な術後指導や生活指導は?
多くの患者様が悩む一つの症状、しびれによる痛み。慢性的な肩凝りも実は神経障害の一つかもしれません。首から肩甲間部、肩上部から胸部、腋そして腕や手のひらから指先のしびれと痛みの部位によって、その症状のメカニズムは多岐にわたります。これまで従来の神経学的なアプローチに経絡を介した遠隔からのアプローチに置き換えながら組み立てていくことで施術効果は飛躍的に上がり患者様を悩ませる苦痛を取り去ることが早期に実現します。様々な病理に対応したアプローチ方法を学習していきます。
- 上肢のしびれと痛みは経絡病証と臓腑病証で分類すると病理の違いは?
- 下肢のしびれと痛みは経絡病証と臓腑病証で分類すると病理の違いは?
- 上肢にしびれや痛みの症状に対する鍼灸治療は?
- 下肢にしびれや痛みの症状に対する鍼灸治療は?
- 症状の出ている経脈を脈診で確認する方法は?
- しびれや痛みがある時の脈状は?
- 原因が頸部にあるしびれをアプローチする遠隔部の経穴はどこ?
- 正中神経障害、橈骨神経障害、尺骨神経障害の際に使用する遠隔部位の経穴は?
- 胸郭出口症候群の際に使用する経穴は?
- 原因が腰部にあるしびれをアプローチする遠隔部の経穴はどこ?
- 大腿神経痛、坐骨神経痛の際に使用する遠隔部位の経穴は?
- 術後指導や生活指導は?
罹患する患者数は腰痛の方が多いですが、一人あたりの来院頻度が腰痛よりも多い膝関節痛。人体の中で股関節に次ぐ大きな荷重関節でもあるために治りにくく、西洋医学な保存療法では限界があり、最終的には手術を回避するために鍼灸施術に頼るケースが少なくありません。西洋医学的にも原因が明らかにならないものや変形が著しいものもありますが、患者様が来院された時に痛みをゼロにする施術を行い、それを維持できれば、継続加療することにもつながり悪化しないまま完治することが可能になります。鍼灸施術を受けるまで経過や背景の長い患者様に対応できるアプローチ方法を紹介していきます。
- 東洋医学的な「膝」についてと膝の構成にどのように考えるの?
- 膝関節痛を東洋医学ではどのように説明するの?
- 東洋医学的に「変形」ってどのように考えるの?
- 原因が分からない膝関節痛へのアプローチ方法は?
- 膝関節痛に直接アプローチしない方法って?
- 膝関節痛に必要な術後指導と生活指導は?
鍼灸治療を受ける方が圧倒的に多い肩関節痛は 「いわゆる五十肩」と考えていますが、進行期と拘縮期の肩関節周囲炎、特に慢性化した退行期の肩関節が関節拘縮した状態には手を焼かれていると思います。これは局所の肩関節だけをアプローチしていくだけでは改善しません。そのような場合には経絡を介した遠隔部位からのアプローチ方法がとても有効です。実技練習の前に肩関節にトラブルがある受講生にデモンストレーションを受けてもらい、有効性を確認してから、受講生同士で練習してもらい、臨床ですぐに実践できるようにしていきます。
- なぜ肩関節周囲炎になるの?
- 原因の特定できない肩関節の痛みを東洋医学的ではどう考えるの?
- 経絡を介したアプローチ方法はどうやるの?
- 急性の肩関節痛の遠隔治療について
- 慢性の肩関節痛の治療について
- 肩関節が拘縮している場合のアプローチ方法はどうやるの?
- 経絡を介して鎮痛や関節可動域をアップさせるアプローチ方法は?
- 術後指導と生活指導について
- 急性の肩関節痛の場合
- 慢性の肩関節痛の場合
急激な外力によって受傷し、即時に症状が完成する急性外傷。日常生活に多くの支障を残すためにできるだけ早期に改善させ治す必要があります。鎮静作用・鎮痛作用を得意とする鍼灸施術を積極的に介入することで、主に急性外傷の治療を担う整形外科や柔道整復師よりも早く治癒起点を初動させられることを学校教育では教えません。その積極的なアプローチ方法について共有していきます。
そして9月から12月までに共有した整形外科疾患にも応用・多用できる「皮内鍼法」を共有し、実技練習していきます。
- 外傷って病因のうちのどれに分類させるの?
- 捻挫の病理と病証とは?
- 打撲や挫傷の病理と病証とは?
- 骨折の病理と病証とは?
- 捻挫の古典とは?
- 打撲の古典とは?
- 骨折の古典とは?
- 急性外傷の時の本治法や標治法は?
- 捻挫・打撲・挫傷の局所治療とは?その時の注意点は?
- 骨折の局所治療とは?その時の注意点は?
- 急性外傷の時の術後指導・生活指導は?
- 予想される経過について
- 皮内鍼の特徴って?
- 皮内鍼の適応って?
- 皮内鍼の不適応・禁忌って?
- 貼付後の指導・注意点って?
- 経絡病証による皮内鍼について
- 臓腑病証による皮内鍼について
邪(かぜ)は万病のもと。「風邪を治せたら(経絡)治療家として一人前。」と言われるほど風邪(かぜ)感冒症状は鍼灸治療でしか治せないと考えています。そして風邪・感冒症状と似ている症状であり、同じ病因のアレルギー性鼻炎の代表といっても過言ではない花粉症。この花粉症の花粉も風邪(ふうじゃ)に分類しますから、風邪の概念について探究していき、感冒の病理とアレルギーの病理を東洋医学ではどのように考えていくか、その治療法とセルケアの全てを共有します。
- なぜ風邪を引くのか?そもそも感染するのは何故か?
- インフルエンザや新型コロナウィルスに感染し、発症するのは何故か?
- なぜ鍼灸治療で風邪が治せると言えるのか?
- 風邪薬を服用すると治るどころか悪化して、経過が長くなるのはなぜか?
- 風邪の原因の風邪(ふうじゃ)とは何なのか?
- のどの痛みや違和感に時に使う経穴は?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 激しい咽頭痛や咳喘息の時に使う経穴は?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 気管支炎の時に使う経穴?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 鼻炎(鼻汁・鼻閉)に使う経穴は?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 胃腸症状の強い時に使用する経穴は?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 高熱(39℃以上)の時に使用する経穴は?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 痰を伴う咳が出ている時に使用する経穴は?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 痰を伴わない(空咳)の時に使用する経穴は?脈診ではどのような脈状になっているのか?
- 風邪・感冒の際の治療原則と治療の際に考慮することは何か?
- 東洋医学ではアレルギーの病理メカニズムをどのように考えるのか?
- アレルギー性鼻炎の脈って感冒罹患の場合と異なるのか?
- 治療方針はどのように考えるのか?
- アレルギー性鼻炎(花粉症)が発症する前のアプローチ方法は?
- アレルギー性鼻炎(花粉症)が発症した後のアプローチ方法は?
- 治療の際に考慮することは?
- 風邪の施術後に患者様に伝えておくべきことは何か?
- 適切な生活指導はどのようなことを伝えれば良いのか?
- 風邪・感冒を予防する鍼灸治療とセルフケアはどのようなことをするのか?
女性が訴える最も多い症状の一つ。疾病名ではなく症状が病気の名前になって定着していますが、様々なメカニズムで発症するため多くの種類が存在します。まずは鍼灸治療が適応できない頭痛と適応できる頭痛を明確にしていき、種類に合わせたアプローチ方法を学習していきます。
- 頭痛を起こす病因は何か?
- その病因はどのようなメカニズムで各種の頭痛を起こすのか?
- 太陽経頭痛とは?陽明経頭痛とは?少陽経頭痛とは?それぞれの脈状とアプローチ方法は?
- 太陰経頭痛とは?少陰経頭痛とは?厥陰経頭痛とは?それぞれの脈状とアプローチ方法は?
- 血管拍動性頭痛に使う経穴は?
- ストレス性頭痛に使う経穴は?
- 頭痛と考えられる頭部の神経痛はどの経穴を使ってアプローチするの?
高血圧は虚血性心疾患、脳卒中、腎不全の発症原因と認識されていますが、無症状のため軽視されているためサイレントキラーと言われています。厚生労働省は男女共に最も通院者率が高い疾患として公表していて、4000万人の高血圧患者いると推定されています。適切な鍼灸治療をすると血圧はコントロールできるので、気温が下降し始める季節の前に受講生に共有して地域医療の一端を担って頂きたいと考えてします。
東洋医学では「厥」「厥逆」と称され、病因と病理・病証を理解し、実技練習では「厥」「厥逆」を解消する方法を共有して、習得していきます。
- 血圧が高くなると不利なことは?
- 高血圧の怖さを患者様に伝えるカウンセリングとは?
- 高血圧に有効な経穴とそのアプローチ方法が?
- 低血圧に有効な経穴は?
- 効果的な食事療法は?
- 減塩生活を送るための秘訣とは?
- なぜ運動療法が有効であるのか?
女性の訴える症状の内、主症状では訴えることが少ないですけど、随伴症状として訴えることが多い症状です。訴えとしては便の量が少ない、硬い、排便しにくい、回数が少ない、便遺残感がある、などですが、我々鍼灸師は通常の排便回数の定義すら知らないことが多いのではないでしょうか。腹部にアプローチせずにスムーズな排便を促す鍼灸治療をしていきます。受講中にトイレに駆け込む受講生も続出する方法を実技では練習していきます。
- 一般的な通常の一日の排便回数は?
- 便秘の定義は?
- 便の内容の内訳は?
- 便秘の分類について
- 便秘の病因とそのメカニズムは?
- 脈診では便秘はどのような脈になるの?
- 便秘に有効な経穴は?
- 便秘の時の食事に気をつけるには?
便通異常として訴えの多い下痢症。概念や分類を理解し、発生機序からも考えていくことはとても重要で、予後不良の下痢症や精密検査の必要性のある下痢症もあります。我々経絡治療家はそれらを問診も含めて、脈診(脈状)から推察していきます。何故便が緩くなるのか。精神的なものなのか?飲食によるものなのか?病因と病理を理解して推察して鍼灸治療を展開していきます。
- 下痢の時の脈状はどのような脈なの?
- なぜ湿邪や寒邪などの外因が下痢を起こすのか?
- なぜ内因(精神的なストレス)で下痢を起こすのか?
- なぜ飲食の五味を偏って摂取すると下痢を起こすのか?
- 急性の下痢に有効な経穴はどこ?
- 慢性の下痢に有効な経穴はどこ?
- 食当たりの特効穴はどこ?
- 下痢症状の際の生活・術後指導は?
花粉症や高血圧症と並び近年罹患率が急激に伸びていますが、まだ国民病の一つとして認識されていない逆流性食道炎。原因と考えられるものは現代社会の生活を反映していることもあり、生活習慣病であると言っても過言ではありません。ほとんど高齢者が胃酸を抑える薬を服用している理由は逆流性食道炎があるためで、近年は若年化している背景があるのでカリキュラムに加えました。
- 逆流性食道炎のチェック項目、10項目とは?
- 東洋医学から考察する逆流性食道炎とは?
- 逆流性食道炎の脈状ってどんなの?
- 逆流性食道炎の所見はどのようなものがあるの?
- その所見を解消する処置は?
- 生活指導において不可欠な食事指導や食事療法は?避ける3つの食材とは?
- 生活指導に運動療法は必要なの?
中級コース
初級コースよりも難易度の高い疾病(臓腑病証)に対応できるアプローチ方法を共有しています。
医療機関を受診しても改善しなかった症状や疾病を学校教育で学習した症候別の経穴や特効穴だけで対応するには限界があると考えています。
本コースで共有するコンテンツは経絡治療が著効するものばかりです。
それぞれの東洋学的な病理を考えられ、経絡系統を併せていくことで有効性を上げられます。その方法を共有していきます。
女性の殆どが生理中、生理前に下腹部痛、頭痛、腰痛に悩まされています。
それらの症状を鎮痛剤などの対症療法で抑えている。中には10歳台から鎮痛剤などを服用している背景から胃癌へと移行していく女性も多いことはあまり知られていません。
器質的に子宮や卵巣が問題となっている場合や婦人科や医療機関で原因がはっきりと判明しない場合の生理痛に対するアプローチ方法を学習していきます。
- 月経と月経痛について
- 様々な月経痛について
- 月経や妊娠に関する東洋医学的な考察は?
- 原因が特定できない月経痛の病理は?
- 原因が特定できている月経痛の病理は?
- 月経のときに現れる脈状って?
- 月経前のアプローチ法と排卵前のアプローチ法は違うの?
- 腹部の硬結や圧痛に対するアプローチ方法って?
- 治療の頻度と回数は?
- 月経困難症と月経前緊張症候群での来院日は違うの?
- 生活指導や術後指導について
子宝に恵まれない夫婦は増加傾向にあり、生殖医療の飛躍的な医療技術の向上であっても少子化に歯止めがかからない状況です。つまり最終的には卵子と精子の力、受精卵と母体の受け入れる能力にかかってきます。そして妊娠率を上げるには患者様の体質を改善する方法以外はなく、経絡治療はこの患者様の「余力」ともいうべき能力を飛躍的にアップする「きっかけ」を与えることが可能です。妊娠や出産には「余力」がとても必要で、経絡治療はその「余力」を増やすことが可能なのです。
- 不妊症の病理は腎だけ衰える腎虚だけで考えるの?
- 不妊症の脈状は?その脈状から考えられる随伴する症状は?
- 婦人科全般に使える経穴は三陰交以外にあるの?
- 要穴でもない三陰交を何故婦人科系疾病では多用するの?
- 女性ホルモンを増やす、働きかける経穴ってどこ?
- 糖質制限を薦められた方に使用する経穴ってどこ?
- 冷えを解消する経穴ってどこ?
- 妊活の精神的なストレスを解消する経穴ってどこ?
- 悪い遺伝を軽減させる経穴ってどこ?
- 卵巣の働きを改善する経穴ってどこ?
- 卵巣や子宮の静脈やリンパの還流を促進させる経穴ってどこ?
- 体を冷やさないようにする生活指導って?
- 子宝に恵まれる食材と食事療法って?
- 子宝に恵まれるセルフケアってどのようなことをするの?
近年の少子化や晩婚化により安産に対する要望が増え、様々な情報から鍼灸治療を妊娠した生活に取り入れる妊婦さんは多くなってきました。その背景として妊娠中の様々な変化に対して体調を整えることが、胎児の発育や母体の影響に及ぼす薬物療法や西洋医学的な治療法では対応できないことが認識されつつあるためです。
鍼灸治療の所見も脈診を重視する経絡治療が妊婦さんに最適だと考えています。新しい‘いのち’の誕生について妊娠を通して東洋医学における発生学を学ぶ機会となります。
- 安定期前に鍼灸治療をしていいのか?
- 東洋医学で妊娠はどのように考えるのか?
- 妊娠の脈ってどんななの?
- 妊娠の滑脈と病脈の滑脈の違いは?
- 東洋医学の発生学と臨月までの脈は?
- 胎児の性別を脈診で把握するには?
- デリケートに考えがちの妊婦さんの治療の大原則とは?
- 妊婦さんが訴える主症状の治療は?
- 悪阻(つわり)
- 切迫流産
- 稽留流産後(中絶後)の出血を止める
- 逆子
- 妊娠中毒症
- マタニティーブルー
- 妊婦さんの生活指導について
- 更に積極的なセルフケアついて
女性のライフステージで最も認知されている症状でその人の人生そのものを反映していると考えられる症候群です。軽度の更年期症状から重度の障害に至るまでの病理と病証を東洋医学的に考察して施術していくことで症状に振り回されずに施術することができます。
- 女性のライフステージを古典ではどのように解釈しているの?
- 更年期を東洋医学的に考えると何?
- 閉経ってどの経脈が閉じるの?
- 更年期に訴える多くの症状の病理は?
- どうして更年期には要穴でもない三陰交を多用するの?
- 三陰交は脾経脈としてではなくてどの経脈に属していると考えるの?
- 女性ホルモンを調節する経穴は?
- のぼせやホットフラッシュに有効な経穴は?
- 冷えのぼせの施術はどうしたらいいの?
- どのような術後指導や生活指導を行うの?
いまだ原因が分かっていないため西洋医学ではステロイド剤に頼る対症療法が通常ですが、鍼灸治療で体質改善を行うことで完治することが可能であると考えています。皮膚疾患、特に「かゆみ」に対する東洋医学に対する考え方やアプローチ方法を学習していきます。
- 病因の1つである風邪(ふうじゃ)について、更に深く概念を考える。
- 皮膚がかゆくなる東洋医学的なメカニズムは?
- 何故、肘窩や膝窩、または顔面部や頭頸部に多くかゆみの症状が出るのか?
- 免疫力を調節する経穴って?
- 皮膚疾患に対応する経穴って?
- かゆみに有効な経穴って?
- デトックス効果のある経穴って?
西洋医学では解決・改善しないケースがほとんどのため小児科ですら対応できないことが多い近年増加している症状。不登校児の理由の一つにもなっている多感な時期を自宅で過ごすことを余儀なくされてしまう。様々なパターンがあって症状に該当する鑑別が必要で身体症状の起立失調症状や自律神経失調症状、精神症状に対しては対症的な薬物療法がされるだけとなり鍼灸治療に頼るケースが多くなっています。我々鍼灸師は対応できるように準備する必要が急務と考えています。東洋医学的な病理観では機序が明確なため経絡治療が著効するケースが散見する得意としている障害です。当会オリジナルの処置方法について共有します。
- 経絡治療を受けた結果、経過や施術回数・施術頻度から統計的に考察するとどのような傾向があるか?
- 当該疾患を東洋医学的に考えるとどのような病理か?
- 当該疾患の病因と病位はどのように考えられるか?
- 当該疾患を西洋医学的に考えるとどのような病理がなるか?
- 東洋医学的に考えた結果のアプローチ方法は?
- 西洋医学的に考えた結果のアプローチ方法は?
単独の主症状として鍼灸院に来院されることは少ないかもしれませんが、愁訴の中では訴える患者様はとても多いです。動悸とはどういうものか?不整脈はどういうものか?から学習して、東洋医学においての動悸・不整脈のメカニズムを学習してきます。このメカニズムは検査をしても問題が見付からない場合に大いに役立ちます。
- 頻脈や徐脈は不整脈に含まれるの?
- 鍼灸治療が禁忌の動悸や不整脈とは?
- 動悸(心悸亢進)が起こる東洋医学的メカニズムは?
- 不整脈を起こす東洋医学的メカニズムは?
- 不整脈の脈状とはどんな脈?
- 動悸・不整脈を予防する経穴って?
- 動悸・不整脈を起こしている時の所見は?
- その所見を解消する処置は?
- 動悸・不整脈の術後・生活指導は?
日本では100人の約6人が一生涯のうちに「うつ病」を経験しているという調査結果があります。女性においては妊娠や出産、更年期などのライフステージにおいて症状が出るケースがあります。このような心(こころ)の、精神的な症状は何故起きるのか。東洋医学では心身を陰と陽で考えていきます。精神や感情などの心の部分は見えないので「陽」として、身体の部分は見えるので「陰」として考えていくと、この見えない心に対してのアプローチ方法がごく簡単に考えられ、対応することが可能となります。メディアをはじめ、我々経絡治療家がうつ病などの精神的疾患に対して有効であることが臨床現場では報告されています。
- うつ病をはじめとする精神疾患の際の医療面接やカウンセリングで必須の傾聴って?
- うつ病になりやすい患者様の思考についての見解
- うつ病の症状ついて
- うつ病の種類について
- うつ病の古典について
- 七情の気が偏勝すると五神が傷られる病理的な機序は?
- うつ病の時の脈状は?
- 精神的なストレスが多い時の所見は?
- その所見を解消する処置は?
- 頭脳明晰にする経穴ってどこ?
- 精神的なストレスに身柱穴が効果的な理由とは?
- 近親者が精神的疾病を患っている経験(家族歴)がある時に有効な経穴って?
- 上記以外で有効な経穴ってどこ?
- うつ病の患者様の治療の際に考慮することは?
- 術後指導・生活指導について
身体の回転感、動揺感、昇降感、傾斜感をめまいとしていますが、めまいの概念は脳貧血を含んで、意識障害を伴った精神的、身体的平衡障害など多岐にわたります。まずは現代医学における分類をし、末梢性のめまいを治療する上で必要な概念と所見を学習していきます。そして東洋医学における分類を季節にめまい、耳に開竅する腎によるめまいで説明していきます。その後に各種めまいの鍼灸治療を実技で練習してきます。
- 貧血と脳貧血の違いって?
- ヒトの平衡感覚って?
- 中枢性のめまいと末梢性のめまいってどう違うの?
- 自律神経失調症や恐怖症もめまいを起こすの?
- めまい全般に使用できる有効な経穴って?
- 天候による憎悪するめまいに有効な経穴って?
- 月経により憎悪するめまいに有効な経穴って?
- 自律神経失調症によるめまいに有効な経穴って?
- 恐怖症によるめまいに有効な経穴って?
- めまいに有効な運動療法はどのようなもの?
甲状腺ホルモンは物質代謝、発育、精神機能に大きく関わり、身体の殆どの組織に影響を及ぼします。過剰に分泌されると全身の臓器細胞の働きが過剰になりますので、肉体及び精神に様々な影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす疾病です。
東洋医学から考察すると甲状腺の機能は右腎(命門)の機能と酷似しています。流注からも考察すると甲状腺は腎経との関連性が高いと考えられます。この腎・腎経と考えられる甲状腺を整える鍼灸治療を共有していきます。
- 多岐にわたる甲状腺機能亢進症の症状を脈状から考えられた病理って?
- 甲状腺腫
- 頻脈、息が荒い、発汗過多
- 生理不順、月経寡少
- 動悸や頻脈
- 食欲亢進、進行すると痩せていく
- 精神症状、神経質
- 眼球突出、眼瞼痙攣、筋力低下、手指振戦
- 甲状腺機能亢進症で現れる所見とその治療点についてどのように決めるの?
- 下垂体に働きかける経穴ってどこ?
- 来院(治療)頻度を決めるうえで考慮する事項って?
- 食事において禁止する食品と制限する食品って?
- 食事において適切な食品って?
全国で70~80万人を超える患者がいると推定されていて、全身の関節の炎症が起きるため、腫れや痛みに苦しみ、次第に関節は破壊されて関節の変形が起こる関節リウマチ。免疫機能の異常と考えられていますが、詳細は不明のままであるために対症療法でしか西洋医学では対応できない現状です。その関節リウマチに東洋医学は体質改善をしながら、関節を破壊しないように炎症を沈め、変形しないアプローチをしていきます。関節リウマチをはじめとする自己免疫疾患へのアプローチに応用できる内容です。
- 東洋医学では関節リウマチ(自己免疫疾患)の症状や病理をどのように考えるか?
- 適応する関節リウマチと不適応の関節リウマチとは?
- 骨破壊を止める処置とは?
- 自己免疫を調節する経穴って?
- 活動期と寛解期の生活指導は?
- 関節リウマチに有効な食事とは?
上級コース
最上コースでは東洋医学的な生理学と脈状を学ぶ内容が中心となります。
経絡治療をより深く学びたい方が勉強するコースです。
脈診で生体を把握して鍼灸治療を展開していく経絡治療家の我々が最も重要視する陰陽(学説)の概念。古典では「あらゆる事象は陰陽の原理の外に出ない」という考えから経脈、臓腑の構造や機能を全て陰陽学説に当てはめ、説明されています。
1359年に脈診の大家、滑泊仁は「身体の陰陽を把握するのは脈診である」。と述べており、身体という小宇宙を陰陽で診ることは世界の本質まで観ていくことにつながるとも述べていました。この陰陽を臓腑の生理学として、もっと深く探究し、学習していきます。
- 陰陽について
- 分類の論理
- 統合の論理
- 盛衰の論理
- 転化の論理
- 可分の論理
- 臓の生理について(肝、心、心包、脾、肺、腎)
- それぞれの臓の精気に陰気と陽気が存在する
- 腑の生理について(胆、小腸、三焦、胃、大腸、膀胱)
- 奇恒の腑の生理について
- 五臓の平脈は何故その脈状をしているのか?
五臓六腑の中で唯一、二つある「腎」。左腎に陰気、右腎に陽気を別々に持ち合わせており生命の根源として存在し、次世代への生命の本である「精・気・神を継承する」機能と生殖、成長に関連し、水分代謝を行うマルチな臓を中心に学習していきます。
脈状では腎の平脈に関係が深い
- 右腎と左腎の位置は?
- 右腎と左腎の機能は?
- 先天性の機能について
- 後天性の機能について
- 腎の平脈と三焦の平脈の脈状は?
- 右腎に関わる疾病と病理について
- 左腎が関わる疾病と病理について
人を治す鍼灸を施すということは、気と血の存在を認識する必要があり、気と血の作用を理解することが不可欠なことと考えています。東洋医学で生命の根源と考える気と血を探究することは永遠に取り組み、日々の臨床に向かうべきです。
- 気とは?
- 原気の生成、働き、流注について
- 精気の生成、働き、流注について
- 営気の生成、働き、流注について
- 身体の全経脈を一日50周するのはどうして?
- 衛気の生成、働き、流注について
- 宗気の生成、働き、流注について
- 血とは?
- 血の生成について
- 血の再生について
- 血の生成と各臓の精気の関係
- 血の循行について
- 血の循行と各臓の関係性
東洋医学の疾病観じゃ天候の変化、過度の精神的感動、飲食の不適、過労などの身体の内界と外界の様々な要因となり、生体内の陰陽、気血、臓腑、経絡などの不調和が引き起こされ、調節困難な状況に陥ると、様々な病的状態を顕します。それを経絡病証と臓腑病証に分類し、病因、病因の伝播、病理を学習していきます。
- 外感、内傷って?
- 病因の特徴とは?
- 疾病の根本原因は?
- 外因の特徴について
- 内因の特徴について
- 不内外因の特徴について
- 五臓の臨床所見と病理については?
五行の中央に鎮座する「土」に配当される臓腑「脾と胃」は五臓の中央で鎮座します。「脾胃」は現代医学の膵臓や脾臓と胃袋の機能として考えるだけでは説明がつかない機能を併せ持っていますが、解剖学では霊枢の腸胃篇で現代医学と同じに正確な詳細を述べています。臨床では当会の経絡治療は中医学の証立てとは異なること。そして消化器症状の際に安易に主証を脾虚証とせずに客証として考えて、陰経の瀉法という他流派と異なったアプローチ法を行います。これは脾と胃は表裏一体となって機能し、他の4臓をコントロールしているためです。
大地の恵みである陰の精気を水穀(飲食物)として摂取し、全身を栄養する「気・営気」を作り出し、さらに「血・営血」や「津液」をも作り出していく脾胃について深めていきます。
- 脾と胃、そして脾胃の生理、位置、構造とは?
- 後天の気(精)とは?
- 胃の気とは?
- 脾胃の蔵象とは?
- 鍼灸治療と湯液(漢方)治療における脾胃に対する相違点とは?
- 脾胃(消化器)の症状をアプローチするうえで注意する点とは?
- 経絡病証と臓腑病証の脾胃のアプローチ方法の臨床例とは?
人体をパトロールする精気の一つである衛気。生成は大腸でなされ、水穀から生成される。黄帝内経の霊枢では衛気の本体は「リンパ液」であり、機能は「神経系」であると考える記述をもとに衛気について詳しく学習していきます。また経絡治療がどうして有効なのか?免疫力を上げることが可能であるのかを学習していきます。
- 衛気とは?
- 衛気の走行順序と機能は?
- 衛気と睡眠について
- 衛気と自律神経の日内変動のゆらぎについて
- 衛気による発汗機序ついて
- 衛気と鍼灸治療について
- 衛気がリンパ液と考えるにあたって三焦がリンパ管と考えるについて
- 衛気は腸内細菌なのか?
- 衛気の状態は脈診ではどの部分で診るのであろうか?
古典で「名有って形無き」と説明される三焦は、本体は衛気や原気を容れる器である全身。六腑としての三焦。そして躯幹を3つに分けてリンパ管とすることが書かれています。それらを学習していき、全身調整する経絡治療が有効なのかを共有していく単元です。
- 躯幹を三つにした三焦の解釈とは?
- 三焦(上焦、中焦、下焦)の経路とは?
- 六腑としての三焦の解釈とは?
- 何故、原気の通り道であるのか?
- 何故、衛気と関係が深いのか?
- 三焦の西洋医学的は解釈とは?
- 三焦病の際にアプローチ方法とアプローチする経穴は?
4月 微脈 / 弱脈 / 濡脈 / 牢脈 / 伏匿の脈
二十九脈ある脈状。入門コースで学習した八祖脈以外の十脈の形状と臨床的意義を学習していきます。
- それぞれ七表・八裏・九道(動)のどれに配属するのか?
- それぞれの脈の形って?
- それぞれの脈の意味(臨床的意義)があるの?
- 伏匿の脈は何故隠れるのか?
- 牢脈は帯びる脈状の完全型なの?
5月~7月は学校教育では学習しない経絡系統について深く学習していきます。経絡治療を施す鍼灸師にとって必ず必要な知識と考えています。それぞれの概念から派生した治療法をこれまで取得した経絡治療にプラスしてアプローチすることで飛躍的に臨床力が向上します。
経筋とは運動器系愁訴を主体とした経絡系統のことです。正経上の流注にあり、流注上の筋肉と関係が深いため運動機能に関係した症状に対して経筋を介した治療はとても有効なアプローチ方法です。
- 経筋とは?
- 経筋による診断と治療について
- 十二経筋(経筋病)の診断点と治療点について
- 足太陽経筋の流注と病症について
- 足少陽経筋の流注と病症について
- 足陽明経筋の流注と病症について
- 手太陽経筋の流注と病症について
- 手少陽経筋の流注と病症について
- 手陽明経筋の流注と病症について
- 足太陰経筋の流注と病症について
- 足少陰経筋の流注と病症について
- 足厥陰経筋の流注と病症について
- 手太陰経筋の流注と病症について
- 手少陰経筋の流注と病症について
- 手厥陰経筋の流注と病症について
- 各部位の治療ポイントについて
「いのち」を機能的に維持するために必要不可欠な構造物でありながら目視できない経脈。そのうちの奇経脈は正経脈とは異なり、分枝でもない存在の経脈の一つ。
次世代へ「いのち」を繋ぐ(維ぐ)役割を担っており、先天の精気と後天の精気、そして邪気を受ける独自のルートとなります。この奇経脈について見識を深め、臨床の際に応用して様々な症状や疾病に対応していきましょう。
実技練習では経絡治療に奇経治療を加えて臨床力を上げる方法を共有していきます。
- 奇経の概要について
- 奇経とは?
- 奇経の病について
- 奇経の病証について
- 奇経治療について
- 奇経治療に用いられる主治穴について
- 督脈の流注について(別絡1)(別絡2)と病証
- 陽濇脈の流注と病証について
- 陽維脈の流注と病証について
- 帯脈の流注と病証について
- 任脈の流注と病証について
- 陰濇脈の流注と病証について
- 陰維脈の流注と病証について
- 衝脈の流注と病証について
「優れた臨床家は十二経脈に精通することの困難さをよく理解しており、慎重に対処している。」と経別篇の第一章で黄帝が述べています。まずは別行の正経と呼ばれる経別について学習して、経絡に対して更に深めて学習していきます。実技練習では臓腑(が関連する)病証で著効する経別治療を是非マスターしてほしいです。
- 経別とは?
- 腎・膀胱経別とは?
- 肝・胆経別とは?
- 脾・胃経別とは?
- 心・小腸経別とは?
- 心包・三焦経別とは?
- 肺・大腸経別とは?
- 補足)絡穴について
- 経別治療の適応症と診断点、治療点について
*カリキュラムは年度ごとや開催状況、世界情勢に合わせて変更する場合があります。
臨床現場で十分に有効な単発受講の内容です。不定期で開催しております。
- 小児鍼法について
- 食養生について
- お灸漬け(灸療法)
- 皮内鍼法について
- 肋間神経痛の鍼灸治療
- 自律神経失調症の鍼灸治療
- 糖尿病の鍼灸治療